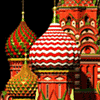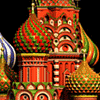聖ヴァシリー教会(ワシリー寺院) St. Basil's Cathedral
モスクワと聞けば多くの人が聖ワシリー寺院の美しくも恐ろしいねぎぼうず型(たまねぎ型)のドームを思い浮かべるのではないでしょうか。 しかしあれは最初からあのようにデザインされたのではないそうです。 このような美しい聖堂を他に作らないように イヴァン雷帝が設計者の目をくりぬいたという伝説は事実ではないそうですが、 イヴァン雷帝の残忍なキャラクターとともに、神秘的な極彩色のドームのイメージがこの伝説に大きく関わっていたことでしょう。 しかし本当はイヴァン雷帝の時代には、ドームはすべてビザンツ風の丸い形で、色もすべて金色だったと考えられているそうです。 たまねぎ型にしたほうが積雪に耐えやすいということはあったでしょうが、その他にあえて改装する理由があったのか、 その背景が知りたいところです。また外側の回廊もあとから加えられたものらしく、 そうすると1560年(桶狭間の戦いの年)の完成当初は現在の姿とはかなり違っていたことになります。
Russia St. Basil's History Architecture
私は現在見るようなデザインが最初から完成していたと思いたい気持ちがあったので、そうではないと知って少しがっかり しました。しかし多くの人の手が加わり時間を経て初めて複雑な陰影を持つモスクワのシンボルが出来上がったということなら、 それはこの建物にふさわしい来歴でしょう。そして聖ワシリー教会という名前も、建設当初からのものではないそうです。 名前の由来も含めてここにワシリー寺院についての説明があります。
その名が「聖愚者」に由来するということからも、この聖堂の背後に重厚な文化が隠れていることがうかがえるように思います。(それはロシアを縛るものでもあるかもしれませんが)
建設当初のワシリー寺院が多くの金色の丸いドームを戴いていたとして、それは現在とはまた違う強烈な印象をあたえる姿だったことでしょう。 イヴァン4世(イヴァン雷帝)はカザン・ハン国 に対する勝利を記念してこれを建てました。 これが建てられた背景には苛烈な戦いの歴史があったのです。 2代前の イヴァン3世の時代に すでにロシア(モスクワ公国)は タタールのくびき (加藤研究室の個人書庫)を脱し大国としての 姿を現しつつありましたが、依然タタール人 の諸勢力は大きな脅威でした。イヴァン雷帝はタタール人を打ち破り カザン・ハン国 を併合してその脅威を減らし、国家発展の基礎を築くことに成功しました。 タタール人との死闘の様子はアンリ・トロワイヤ(Henri Troyat)の伝記小説「イヴァン雷帝」(工藤庸子訳、中公文庫)でうかがい知ることができます。(以下5か所を引用します) (「小説」なので書かれていることがすべて史実に合致しているとは限りませんが)
当時の年代記作家は、ロシア国境への蛮族侵入のありさまを、次のように記している。「身を守るべき手段をもたぬ 不幸な住民たちは、森の中や洞窟の奥深く身を隠すしかなかった。以前は村人たちでにぎわっていた土地が、ぼうぼうたる 藪におおわれてしまった。焼け落ちた修道院の廃墟のなかで、異教徒たちが、教会を寝ぐらにして生きていた。 彼らは、聖なる器を食器に使い、聖像の飾りを引きはがして、耳飾りや首飾りをつくり、それで女たちの身を飾った。 燠火(おきび)のまじる熱い灰を修道僧の長靴に注ぎ込み、苦しむ彼らに踊りを踊って見せよと要求した。 若い修道尼たちを犯し、男たちの眼をつぶし、鼻や耳を削ぎ、手足を斬り落とし、残りの者は捕虜として連れ去った。 しかしそうしたことのなかでもっとも恐ろしいのは、多くのキリスト教徒が、彼らの信仰に帰依したということである。(後略)」1547年のロシア軍のカザン遠征は失敗し、1550年に再び挑むもののこれも失敗に終わります。
イヴァンは剣を握りしめ、生まれてはじめて実戦の指揮をとった。とはいえ、身の危険はない。モスクワ大公国の伝統によれば、 君主は戦うのではなく、士気を鼓舞するのである。六万のロシア兵が、城門の割れ目に吸い込まれた、と思う間もなく町中にどっと あふれ、手あたりしだいに住民を虐殺した。だが町の中心にある城塞は、ついに陥落しなかった。翌日、急に雪解けの 陽気になり、激しい雨が降った。これでは次の作戦を展開することができない。火薬は濡れ、砲は発射せず、河の氷は割れ、 道は泥沼と化し、糧食が部隊に届かぬために、兵は飢えに悩まされ、イヴァンは、このままでは洪水のためにまもなく 退路を絶たれるだろうと心配した。悔しさをこらえて、彼は退却を命じた。そして1552年数十万の大軍で行った遠征でもロシア軍はカザン側の激しい抵抗に一時危機に陥ります。
陣地に駆けもどった将軍たちは、ツァーリに対し、祈祷を中断して、危機に陥った部隊のまえに姿を現すよう、何度も懇願した。 臆病さゆえか、あるいは信仰のためか、彼はミサが終わるまで教会の外にはでない、と答えた。 その間にも、カザンでは殺戮がつづいていた。家々の屋根のうえでも、人が戦っていた。激昂したロシア兵は、 女子供にも見さかいなく襲いかかった。女子供はその場で殺してしまうか、さもなければ縛りあげて、あとで奴隷に売るのである。 市場までやってきたロシア兵は、山と積まれた宝物に眼をみはった。金銀の細工物、毛皮、絹織物、・・・・・とたんに 彼らは戦意を失い、略奪をはじめた。カザンの兵は、この無秩序に乗じて、反撃にでた。結局このときの戦いでロシア軍はカザンを制圧します。私はこの見てきたように描写する1911年生まれの作家が、 ワシリー寺院の建設についてどう述べているかを楽しみにこの本を読んだのですが、その部分はこんなふうでした。
建物はほかにまったく例のないようなもの、神秘的な喜悦、ほとばしる歓喜、形と色彩の饗宴とならねばならぬ。 いったい誰を棟梁に選んだらよいだろう。まずイタリア人が候補にあがった。彼らはすでにモスクワで実績をあげている。 しかし、ロシアの勝利を象徴する建築を建てるには、ロシア人がふさわしい、というわけで、結局、バルマ・ヤコーブレフ、 通称ポストーニクという建築師に白羽の矢が立てられた。まるでツァーリの矛盾する人格のすべてを投影したような この奇妙なモニュメントを建造する大任を、彼が果たすのである。しだいしだいに、まるで地面から生えるように、この 異様で崇高な大寺院がその全貌を現した。不ぞろいな八つの丸屋根の上に、金の玉葱をのせたピラミッド型の鐘楼がそびえ立つ。 あるものは畝を彫り、あるものは鱗をはり、あるものは切子面に削った極彩色の葱ぼうずは、青空に象嵌したように一分の 隙もない。食人鬼に捧げるために用意された幻想的な果物籠とでもいおうか・・・・・工事には六年を費やした。 その費用は、当然のこととして、賠償金という名目でカザンの住民からとりたてられた。
当時はそんな形と色ではなかった、という事を知ったあとでこれを読むと、ほんの少し興ざめという部分もありますが、 ドームについての描写はみごとではありませんか。なお、ここに「畝を彫り」とか、「切子面に削った」とあるのは比喩で、 実物は板金のたたき出しのようです。建築家の目をくりぬいたという伝説はさすがに無視しています。 ところでワシリー寺院は「ポストーニク」と「バルマ」という二人の建築家が設計したという説も広く流布しているようですが、 どちらが本当なのでしょうか。
この本には他にもワシリー寺院が出てくる部分があります。
刑場はクレムリンの中央広場。すぐそばには完成したばかりのポクロフスキー寺院(ヴァシリー・ブラジェーンヌィ寺院) のにぎやかで多彩な丸屋根が、陽気に輝いている。カザン攻略の英雄、 アレクサンドル・シュイスキーとその息子、今年17歳になる ピョートルが、まず血祭りにあげられた。アンドレイ・クルプスキーと共謀して、君主とツァーリツァ、そして子供たちの 命をねらったためである。はじめに息子が首を斬られるはずだったが、父親は最後の願いとして、先に処刑していただきたいと 申し出た。役人は快く承知して、アレクサンドル・シュイスキーが首を台のうえにさし出した。斧が振りおろされた。 息子は、ころがりおちた父の頭を拾いあげて優しくくちづけし今度は自分の首に斧の一撃を受けるため、処刑台に跪いた。 同じ日に、さらに六名の大貴族が斬首刑になった。七人目の大貴族、ディミトリー・シチェヴィレフ公は、串刺しの刑に処された。 彼は肛門から串を差し入れられたまま、苦痛で顔をゆがめ、神を称える聖歌を歌いつつ、二十四時間苦しみぬいて、死んだ。
最後に出てくる串刺しの話はこの本に出てくるイヴァン雷帝のおびただしい残虐行為のごく一部にすぎません。 私はこのディミトリー・シチェヴィレフ公が実在の人物かウェブで調べようと試みましたがわかりませんでした。反逆の疑いをかけられた人物に 対しその容疑の真偽に関わらずこのような残虐行為が多く行われたことは事実のようです。 たまたま私の手元にある「ライフ人間世界史第16巻・ロシア」(原著ロバート・ウォーレス、日本語版1968年) という本で、ロシアに滞在した英国人ジェローム・ホーシー(Sir Jerome Horsey) による記録として似た話が紹介されいるのを見つけました。
(前略)彼の残虐行為については、イギリス人ジェローム・ホーシーのような外国人によっていくつかの記録が残されているが、原文の 表現を手直ししなければ、とてもここには紹介することはできない。
”ボリス・テレプネフ公は、皇帝に対する反逆者であることが露見して、先端をとがらせた長い杭の上に引き落とされた。杭は身体の下の 部分に突き刺さって、首から飛び出た。杭の上で彼は恐ろしい苦痛に身を弱らせながら、15時間生き続け、悲惨な光景をながめさせる ために連れてこられた母の公爵夫人に話しかけた。公爵夫人はなかなか品のよい女性だったが、100人の砲兵に与えられた。彼らは彼女を 冒涜して死にいたらしめ、皇帝の飢えた猟犬どもが、彼女の肉と骨をむさぼり食った。”
この話は"Boris Telupa"で検索するとたくさん出てきます。
カザン・ハン国を併合してタタール諸勢力の脅威は大幅に減少したはずでしたが、モスクワが完全に安泰となったわけではありませんでした。 上述「ライフ人間世界史第16巻・ロシア」から再び引用します。
それでもクリミアのタタールは侵入してきた。1571年彼らはモスクワに襲いかかって、市内を焼き払い、すくなくとも10万の市民を殺すなど (そこに住んでいたあるイギリス人は、80万という数字をあげている)、暴虐のあらん限りをつくした。これは数人のボヤール が、無防備な道筋をタタールに教えたからだといわれている。モスクワ川は死体で埋まって流れの向きが変わり、川の水は数キロ下流まで紅に染まった。 撤退していったタタールは、数百人の市民を奴隷として連れ去った。若い娘が多かった。彼女らは、タタールの鞍につけられた籠に入れられ連れていかれた。 しかし、くさりでつながれていても、ロシア人は扱いにくかった。彼らは執念深く脱走をくわだてる。奴隷商人たちはビザンティンで商品を売るときには、 必ず奴隷は"王国"(リトワニア)から連れてきた者で、ロシア人よりは御しやすい、と強調していたという。
ワシリー寺院はどれほど多くの、個人の力ではどうすることもできない災厄がふりかかった人々の苦しみを見てきたことでしょう。ワシリー寺院自体も1812年にナポレオンがモスクワを占領し、撤退する際、破壊されそうになったこともあったそうです。 しかし数百年の風雪と戦火に耐え、今も深い陰影を刻んだその姿を見せています。